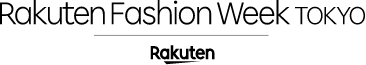Shogo Yanagi 柳 翔吾
FAKE TOKYO チーフ&PR CANDY マネージャー
大学在学中、「エース」(元「ジプシー」&「バサラ」)にてインターンを経験。大学卒業後にラフォーレ原宿「Side by Side」に入社。その後CANDYへ入社し、在学中での渡英経験を活かし、バイイング業務、PR業務を担当する。2010年、CANDY、Sisterからなる渋谷の新ファッションスポット「FAKETOKYO」を現ディレクター伊藤と共に立ち上げ、ショップマネージャーとしてPR業務を中心に店舗ディレクションを行う。現在、同ビル3Fに「FAKE SHOWROOM」を新たに立ち上げ、国内若手ブランドのセールス・PR・コンサルティングを中心に、衣装制作や、アーティストの衣装ディレクションを行う。
[ CANDY ] http://www.candy-nippon.com/
[ Sister ] http://sister-tokyo.com/
国内外のカッティングエッジなブランドを取り揃え、最先端のファッションを独自の世界観で提案するセレクトショップ CANDY。2010年には、新宿二丁目から、より雑多な人種、多様な情報が集まる街、渋谷のセンター街に移転。姉妹店の Sister、若手デザイナーの発掘、流通などを行うFAKE SHOWROOMとともに、新たなファッションの提案を行う一大拠点を築き、そのコミュニティをさらに拡大させている。
これらの活動を展開する FAKE TOKYOのディレクションや、CANDYのマネジメント・PRなどを手掛ける柳 翔吾氏にインタビューを行った。

CANDY 外観
柳さんがCANDYに関わるようになったきっかけを教えて下さい。
学生の頃からの知り合いで、CANDYで働いていた友人がいて、ちょうどショップの方向性を変えていくというタイミングで誘われたのがきっかけです。そこで一緒に店作りをしていく中で、自分のファッションに対する考え方をダイレクトに表現することができて、すごく楽しかったんですね。それに対するお客さんからの反応もあって、大きな可能性を感じました。
CANDYに入る前は何をされていたのですか?
大学生の頃から、当時代官山にあった「ジプシー(GYPSY)」というセレクトショップで働いていました。セレクションが最先端かつアンダーグラウンドなショップで、そこでの経験が僕のファッションの原体験になっています。大学卒業後は、ニコラ・フォルミケッティがディレクションしていたラフォーレ原宿内の「Side by Side」というショップで働き始めたのですが、1ヶ月半後に閉店することが決まり……。ちょうどファストファッションの大きなショップが東京に進出し始めていた頃で、新しいブランドをピックアップしていた最先端のショップがどんどんなくなっていく感覚もありました。“それなら自分たちで提案していこう!”という思いで、CANDYのリニューアルに関わっていたような気がしています。
CANDYのディレクションにおいて大切にしていることを教えて下さい。
新しいブランドに注目するようにしています。ただ若手のブランドであれば良いというわけではなく、表現が振り切れているかどうかというところを基準にしています。極端な話、たとえパターンや縫製の技術が劣っていても、自分たちの世界観や見せ方を追求できているブランドは、その後、色々な経験をしていく中でクリエイションが研ぎ澄まされて、良い方向に向かっていくことが多いんです。最近は、学生のショーなどを見る機会も多いのですが、全体的にキレイにまとまりすぎている気がします。ゴスロリ、パンク、ヒップホップなど何でもいいのですが、もっと自分たちの表現を突き詰めていってほしいなと感じることが多いですね。
新宿二丁目から渋谷に拠点を移して2年が経ちますが、どんな変化がありましたか?
高校生やギャル、周辺のアパレルショップの店員さん、デザイナーさんなど、色々な人が来てくれるようになりました。新宿時代は周りに洋服屋なんてなかったので、何にも影響されずに自分たちの世界観を伝えられる良さはあったのですが、その反面なかなか人が訪れづらい場所でもありました。僕たちとしては、これからオシャレをしてみたいという人たちを育んでいきたいという思いもあるので、自分たちから前に出て行って提案していくことが必要だとも考えています。だからこそ、あらゆるものが揃っていて、様々な国籍、世代、スタイルの人たちが集まっている渋谷という街に来たかった。ここに来てくれる人たちは皆、それぞれのスタイルにプラスアルファやオリジナリティを持たせるための何かを求めていて、そういうお客さんに対して、まずはスタイリングの提案をしていくことで、いずれはその洋服を作っているブランドの世界観にも興味を持ってもらえたらなと考えています。

デザイナーとの関係性についてはどんなことを意識していますか?
若手ブランドの登竜門でありたいと思っています。そういう場所がひとつあると、作り手の人たちの目標になって、モチベーションも高まりますよね。ファッション・ウィーク期間中のロンドンに行った時に、セルフリッジやブラウンズといったデパートやセレクトショップが、まだランウェイショーもしていないような若手ブランドに、ウィンドウディスプレイの場を与えていたんですね。日本ではなかなかそういう大きな力を動かすことは難しいですが、小さいなりにも自分たちがまずはがんばっていくことで、もっと盛り上げていけたらなと思っています。
CANDYで取り扱いのある若手ブランド同士が合同展示会をするなど、横のつながりも強そうですね。
それはあまり意識しているわけではないんです。結局、個々のブランドがそれぞれの見せ方を確立できていないから、集団になっている部分もあると思うんです。世界観を共有することでできることもありますが、別個に考えていく部分がないと、その先のクリエイションは生まれないんじゃないかと感じています。そこで最近は、僕らがそのきっかけを作っていくということも意識して、アーティストの衣装制作の仕事をCANDYで取り扱いのあるブランドのデザイナーに依頼するなど、普段とは違うクリエイションの機会を与えるようにしています。
セレクトショップ以外の活動も色々されているようですね。
そうですね。CANDYや上のフロアにある姉妹店のSisterでは、しっかりお客さんとコミュニケーションを取りながら洋服を売っていくということをしていますが、そうした動きとは別に、アーティストの衣装制作やファッションディレクションなどもしています。FAKE TOKYOとしては、若手ブランドの洋服を自分たちのお店に卸すだけではなく、ディストリビューションやコンサルティングなどを通して、自分たちが考えるファッションの世界観をグローバルに展開していけたらと考えています。最終的には、そうした動きがショップの方にも還元されて、コミュニティがより盛り上がっていけばいいなと。


外国人のお客さんも多く訪れると思いますが、東京発信のショップという意識はありますか?
最近は、かなり外国人の方も増えてきているので、責任や使命を感じますし、今の東京はこうなんだということをしっかり伝えていこうと思うようになりましたね。だから、若手の日本人クリエイターなども、もっとフューチャーしていきたいと考えています。
東京のファッション・ウィークについてはどのように感じていますか?
最近は、全体的にエンターテイメント性が求められすぎているような気がします。消費者を巻き込みながら何かをするという流れが増えていますが、コレクション会場でそれをやる必要はそんなにないと個人的には思います。ファッションショーはしっかりプロに向けてやるべきで、その辺がやや中途半端になっていて、軸がブレてしまっているような感じがします。まずは東京という場所でしっかりショーを見せていくことで、認知度をより高めることが必要なのかなと。国内でのファッション・ウィークの存在や文化的価値が認められれば、結果的にそれがアジアや世界にも浸透していくのではないでしょうか。
セレクトショップという立場から、ファッション・ウィークとの関わり方について考えていることはありますか?
やはりファッション・ウィークは、日本における一大ファッションイベントなので、自分たちもそこに対して働きかけていきたいという思いはあります。次回から渋谷ヒカリエがメイン会場になるので、その点はとても楽しみですね。僕らがショップでエキジビションやゲリラショーなどをしている理由のひとつは、お客さんにそれを見てもらうことで、デザイナーたちがなぜそういう表現をしているのかということを考えたり、レセプションなどで直接本人と話をすることを通して、ブランドの世界観やコンセプトを考えてもらいたいからなんです。それは、コレクションの前段階とも言える部分だと思うのですが、そうしたコンテンツや見せ方を、ショップなどが主体になって、消費者、バイヤー、エディターなどに伝えていく必要もあるのかなと思っています。
最後に、今後の展望について教えて下さい。
僕らが学生の頃は、エディ・スリマンなどが提案するモードファッションに憧れたり、常に新しいブランドを紹介する尖ったセレクトショップにすごく影響を受けてきたし、突き動かされるものがあったんです。今度は、ショップをやっている自分たちの立場から、それをいかに伝えていけるかということが大事だと思うし、FAKE TOKYOとしては、ショップという形態だけにこだわらず、ファッションの提案の仕方をトータルで考えながらやっていけたらと考えています。