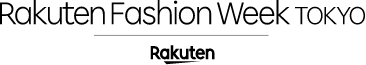津野 青嵐 Seiran Tsuno Seiran Tsuno / ファッションデザイナー
ファッションデザイナー
1990年長野県出身。看護大学を卒業後、精神科病院で約5年間勤務。大学時代より自身や他者への装飾を制作し発表。病院勤務と並行してファッションスクール「ここのがっこう」へ通い、ファッションデザインの観点から自身のクリエーションを深める。2018年欧州最大のファッションコンペITSにて日本人唯一のファイナリストに選出。
[ Instagram ] https://www.instagram.com/seirantsuno/
[ Twitter ] https://twitter.com/tsunoshit
3Dペンで制作した色とりどりのドレスで、イタリアで開催されている世界的なコンテスト「ITS 2018」のファイナリストに日本人として唯一ノミネートされた津野青嵐氏。看護大学に通う傍ら、白塗りメイクで原宿の街を歩き、学生時代から知られる存在だった彼女は、ヘッドピースデザイナーとしてキャリアをスタート。ファッションスクール「ここのがっこう」で才能を開花させ、今国内外から最も注目される新人クリエイターだ。Amazon Fashion Week TOKYO 2019 S/Sのキービジュアルの衣装制作も手がけた津野氏に話を伺った。
ファッション・ウィークのキービジュアルの衣装を担当することになった経緯からお聞かせください。
今回、アートディレクターの大島慶一郎さんをはじめ制作スタッフの皆さんの間で、ボリューム感がある蛍光色の衣装というイメージがあったそうで、ITSの作品を見てくださっていたスタイリストの飯嶋久美子さんからご連絡をいただきました。当初は、ITSに出していた蛍光ピンクのドレスを使いたいというお話でしたが、硬い素材でつくられていたため、モデルさんが着用してジャングルジムを登り降りする今回の撮影にはそぐわないということになり、柔らかい素材を用いて新たに衣装をつくることになりました。
衣装の制作は順調に進みましたか?
今回の制作では、これまでに使ってきたプラスチック樹脂よりも柔らかく、スマートフォンのケースなどによく使われているゴム製の素材を使うということが大きなチャレンジでした。以前から注目していた素材ではありましたが、ぶっつけ本番に近い形でつくり始め、完成したのは撮影当日の朝7時でした。しかも、いざ試着をしてみるとこれまでの作品のように造形的なフォルムを保つことが難しく、正直かなり焦りました。私は撮影には立ち会えなかったのですが、現場に入ったアシスタントから衣装をまとった新井貴子さんの素敵な写真が送られてきて、とても安心したことを覚えています。
今回のキービジュアルの衣装制作を振り返ってみて、どんな感想をお持ちですか?
イメージしていた完成形とは少し違うものができましたが、素材の柔らかさが独特のたゆみを生み出し、これまでとは違う見え方になったことは新鮮で、大きな発見となりました。また、ディレクションや撮影をする方によってこうも印象が変わるものか、と驚きました。そして、キービジュアルが渋谷ヒカリエや表参道ヒルズで大々的に展開されている光景を見た時はとても感動しました。
3Dペンで衣装をつくるという斬新な手法は、どのようにして生まれたのですか?
色々なリサーチをしている中で3Dペンの素材を見つけたことがきっかけです。私が通っていた「ここのがっこう」では、既存の服づくりの技術や方法論にとらわれず、新しい人間像を提案するということに重きを置いていて、それまでにもガムテープやゴミなどを素材に、縫製しない洋服をつくったりしていました。もともと服づくりの知識も技術もない自分に何ができるのかということを考えていく中で、3Dペンと出会い、これを用いた試作品を父に着せた時に、まるで幽体離脱をしているかのように見えたことから、「身体から離脱するネックレス」という作品のコンセプトが生まれました。
「身体から離脱するネックレス」というコンセプトについて、もう少し詳しくお話いただけますか?
幽体離脱を起点にリサーチを重ねていく中で、日本人独自の魂の捉え方が見えてきました。日本人は古来、魂はずっと身体の中だけにあるものではなく、時に浮遊しているものと考えてきました。魂の、ふとした瞬間に抜け出てしまうような、不安定な存在という部分が自分の作品とリンクしていき、このようなコンセプトにつながっていきました。
3Dペンを用いた服づくりの工程についても聞かせてください。
もともと3Dペンは、3Dプリンタで出力したものを微調整する道具として開発されたもので、プラスチック樹脂などの素材が熱されることで溶け出し、絵を描くように自由な造形がつくれるという仕組みになっています。現在は子どもの遊び道具としての用途が主流になっていますが、私はこのペンを使って1本ずつ線を重ねていくことで衣装をつくっています。トルソーに肉付けしながら全体のフォルムを固め、そこに沿うように3Dペンで形をつくっていくというのが大まかな制作の流れです。
海外でも高く評価されている津野さんの作品ですが、国内外で反応の違いなどを感じることはありますか?
日本ではニュースなどのメディアで3Dペンを使ってドレスを作っているという新しい発想の部分で注目していただくことが多いですが、海外ではファッション系の媒体からファッション表現として評価をしていただくことが多いです。自分自身もモードの表現に強い憧れを持ち、ファッションデザインの道に進んでいるので、そういった評価をとてもうれしく思います。自分の肩書についてよく質問されるのですが、皆さんが思う見え方でいいと思います。
International Talents Support
そんな津野さんのこれまでのキャリアについてもお聞かせください。
もともと私は何かを表現していくような生き方を望んでいましたが、両親が保守的だったこともあり、手に職を持つために看護大学に進みました。当初は医療の分野に興味はなかったのですが、精神科病院に実習に行った時に統合失調症の患者さんと接し、その表情や言葉づかい、佇まいなどに感動したことがきっかけで、精神科病院で働くことになりました。現在は制作などで病院勤務が困難になり退職してしまいましたが、今でも地域の仕事として精神保健福祉に関わっています。
看護師としての経験は、ご自身のクリエーションに影響を与えていますか?
直接的に影響していることはないかもしれませんが、精神科の患者さんたちに魅了されたのは、自分と共鳴する部分があったからなのだと思います。精神科病院というのは社会から蓋をされがちな存在ですが、もともと私は社会から逸脱しているようなマイノリティの表現に大いに影響を受けてきましたし、そういうものにしか力を注げないのです。精神科の患者さんからも多くのエネルギーをもらっていますし、彼らの世界にいることでとても心が落ち着く。こうした感覚を表現するために作品をつくっているのかもしれません。
津野さんはヘッドピースの制作からものづくりをスタートしているそうですが、もともとファッションには興味があったのですか?
体型の関係でずっと祖母と同じ縫子さんに洋服をつくってもらっていたので、市販の洋服を選んだり、買ったりすることには昔からリアリティを持てませんでしたが、John GallianoやAlexander McQueenの作るオートクチュールのショーには夢中になっていました。だから、同年代の中でもカジュアルめのファッションブランドへの興味は薄く、もっと極端な装いへと関心が向き、学生の頃から白塗りのメイクをして原宿に出かけるようになったのかもしれません。表現に関わることがしたいという思いを持ちながら、看護大学という将来へのレールがしっかり敷かれたところにいるもどかしさや葛藤を感じていた自分にとって、異世界の住民のようなスタイルをして、色々な人に興味を持ってもらうことが心地良かったんです。その延長としてヘッドピースをつくるようになり、プロの道を模索する中で「ここのがっこう」に出会い、そこで先生からヘッドピースよりも服づくりの方が向いていると言われ、ファッションの方に進むことになったんです。
今後はどのような活動をしていきたいですか?
私の作品をもう少し売りやすいものにしていくためのアイデアなどを周囲の方々から提案されることもありますが、そもそも私にそれは求められていない気がするし、おそらくやろうとしてもできません。この1年間で色々なことが大きく変わったので、今はもう少し自分のクリエーションを深める時間がほしいと思っている段階です。表現の部分に関しては、3Dペンに色々な素材を混ぜていくことでさらなる可能性を追求してみたいと思っています。今後は「絞り」などの日本の優れた伝統技術を現代の素材と融合させた表現も模索していきたいですね。
Interview by Yuki Harada