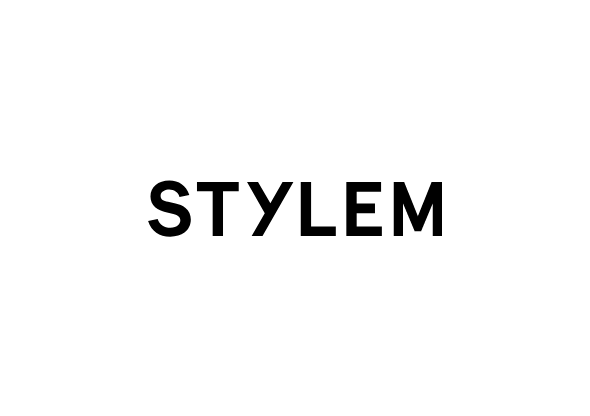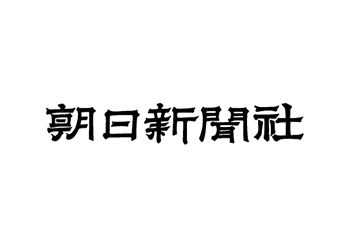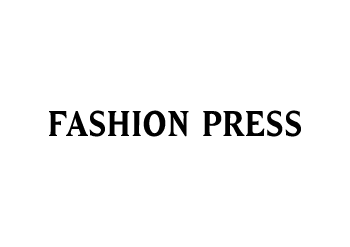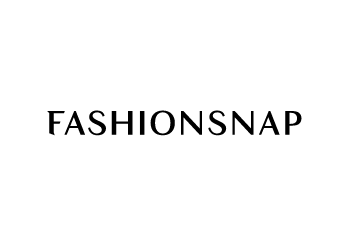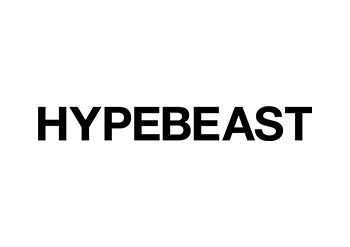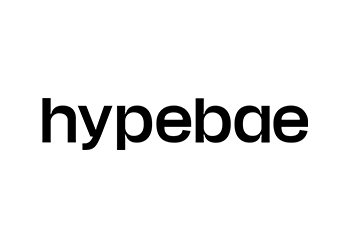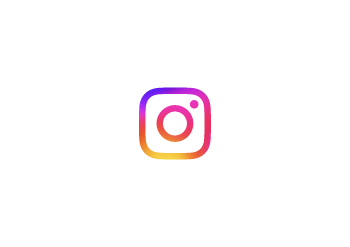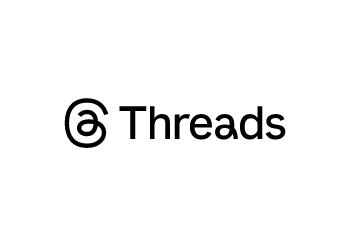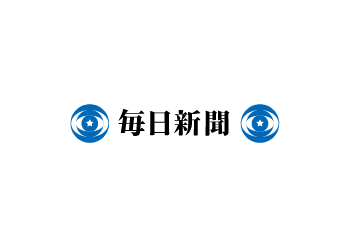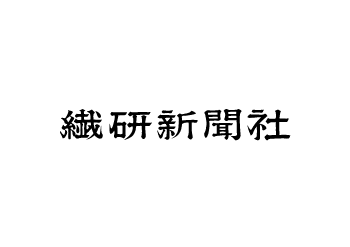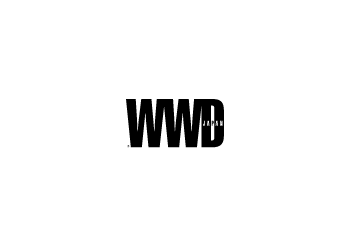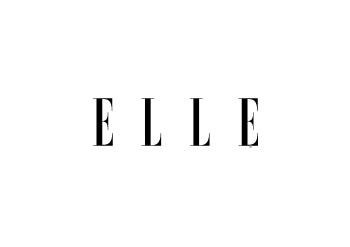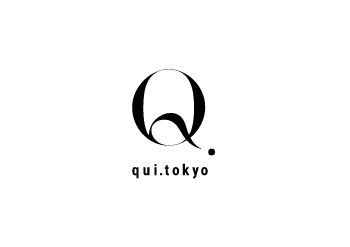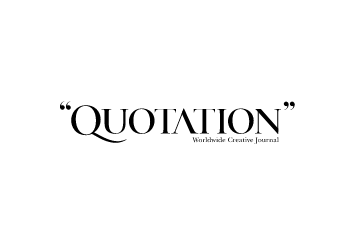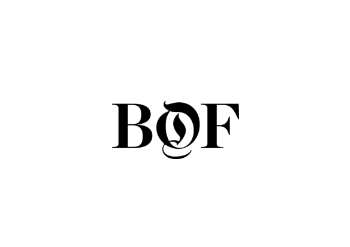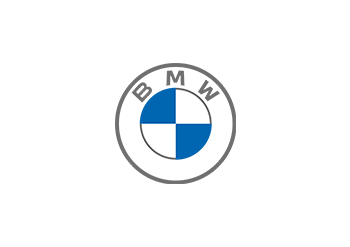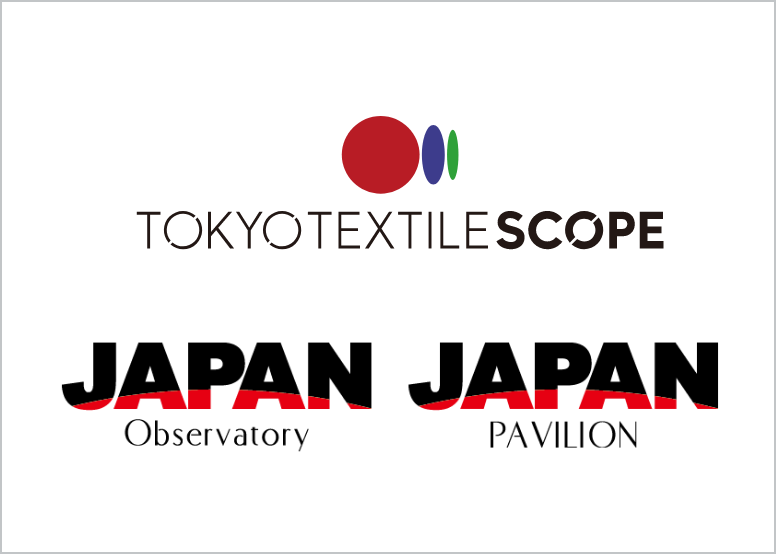Rakuten
Fashion Week
TOKYO
2026 AW MON. 03/16–
SAT. 03/21/2026
Fashion Week
TOKYO
2026 AW MON. 03/16–
SAT. 03/21/2026

TOPICS

Rakuten Fashion Week TOKYO 26AW ショースケジュール発表(2026年2月17日時点)
INFORMATION

[ANTHEM A] 初参加アンケート26AW
PICKUP

26AW シーズン コレクションハイライト
INFORMATION

JFW 20th Anniversary Podcast RE;MODE_ROOM20
PICKUP
SCHEDULE
[ CONDITION TO PARTICIPATE ]
[ BRAND ]
SUN.03/15/2026
10:30-19:00
12:00-12:00
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
12:00-20:00
ORIMI
オリミ
プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
ORIMI オフィス
招待状が必要。プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
15:00-17:00
YEAH RIGHT!!
イェーライト
18:00-19:00
18:00
MON.03/16/2026
10:00-18:00
10:30-19:00
11:00-20:00
11:00-20:00
12:00
12:00-12:00
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
12:00-20:00
ORIMI
オリミ
プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
ORIMI オフィス
招待状が必要。プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
13:00
14:30
15:00-17:00
16:00
17:30
18:45
20:45
TUE.03/17/2026
10:00-18:00
10:30-19:00
11:00-20:00
11:00-20:00
12:00-12:00
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
12:00-20:00
ORIMI
オリミ
プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
ORIMI オフィス
招待状が必要。プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
13:00
14:00
16:00
19:00
WED.03/18/2026
10:00-18:00
10:00-19:00
HISUI
ヒスイ
事前登録をお願い致します。
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
トラノイトウキョウ ベルサール渋谷ガーデン
https://www.tranoi.com/e/tokyo/ja/registration/registration事前登録をお願い致します。
10:00-20:00
10:00-19:00
10:30-19:00
11:00-20:00
11:00-20:00
Millanni
11:00-20:00
12:00-12:00
12:00-20:00
A Good Bad Influence
For Buyers
Designer
Ryoichi Kudo
Mobile: 080-7973-4460
Sales
Keisuke Hosoi
090-1560-2743
For Press&Stylist
Christian Pearson
Mail : Team@eleventil.com
アクセス
表参道駅A2出口を出て徒歩3分。
A2出口前 アップルストア
→隣の原二本通りを突き当たり左(フライングタイガーの方へ)曲がる。
→アフタヌーンティーを過ぎてすぐ右へ曲がる。
→2ブロック先の角のセブンイレブンを左に曲がる。
→右手の3軒目(白とピンクの2色の建物がありその隣)のところになります。
小さいベージュの看板が目印です。
建物が奥まっていますが、階段上がってすぐ右手の部屋となります。
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
O-Studio OMOTESANDO
バイヤー様につきましては、アポイントメント制とさせて頂いております。For Buyers
Designer
Ryoichi Kudo
Mobile: 080-7973-4460
Sales
Keisuke Hosoi
090-1560-2743
For Press&Stylist
Christian Pearson
Mail : Team@eleventil.com
アクセス
表参道駅A2出口を出て徒歩3分。
A2出口前 アップルストア
→隣の原二本通りを突き当たり左(フライングタイガーの方へ)曲がる。
→アフタヌーンティーを過ぎてすぐ右へ曲がる。
→2ブロック先の角のセブンイレブンを左に曲がる。
→右手の3軒目(白とピンクの2色の建物がありその隣)のところになります。
小さいベージュの看板が目印です。
建物が奥まっていますが、階段上がってすぐ右手の部屋となります。
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
12:00-20:00
ORIMI
オリミ
プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
ORIMI オフィス
招待状が必要。プレスリクエストは info@sakaspr.jp
バイヤーリクエストは sales@orimi-k.com
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:30
THU.03/19/2026
10:00-18:00
10:00-19:00
HISUI
ヒスイ
事前登録をお願い致します。
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
トラノイトウキョウ ベルサール渋谷ガーデン
https://www.tranoi.com/e/tokyo/ja/registration/registration事前登録をお願い致します。
10:00-20:00
10:00-19:00
10:30-19:00
11:00-20:00
Millanni
11:00-20:00
11:00-20:00
12:00-12:00
12:00-20:00
A Good Bad Influence
For Buyers
Designer
Ryoichi Kudo
Mobile: 080-7973-4460
Sales
Keisuke Hosoi
090-1560-2743
For Press&Stylist
Christian Pearson
Mail : Team@eleventil.com
アクセス
表参道駅A2出口を出て徒歩3分。
A2出口前 アップルストア
→隣の原二本通りを突き当たり左(フライングタイガーの方へ)曲がる。
→アフタヌーンティーを過ぎてすぐ右へ曲がる。
→2ブロック先の角のセブンイレブンを左に曲がる。
→右手の3軒目(白とピンクの2色の建物がありその隣)のところになります。
小さいベージュの看板が目印です。
建物が奥まっていますが、階段上がってすぐ右手の部屋となります。
BY INVITATION ONLY
SHOWROOM
O-Studio OMOTESANDO
バイヤー様につきましては、アポイントメント制とさせて頂いております。For Buyers
Designer
Ryoichi Kudo
Mobile: 080-7973-4460
Sales
Keisuke Hosoi
090-1560-2743
For Press&Stylist
Christian Pearson
Mail : Team@eleventil.com
アクセス
表参道駅A2出口を出て徒歩3分。
A2出口前 アップルストア
→隣の原二本通りを突き当たり左(フライングタイガーの方へ)曲がる。
→アフタヌーンティーを過ぎてすぐ右へ曲がる。
→2ブロック先の角のセブンイレブンを左に曲がる。
→右手の3軒目(白とピンクの2色の建物がありその隣)のところになります。
小さいベージュの看板が目印です。
建物が奥まっていますが、階段上がってすぐ右手の部屋となります。
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
13:30
14:30
16:00
19:00
20:30
FRI.03/20/2026
10:00-20:00
10:30-19:00
11:00
11:00-20:00
Millanni
11:00-20:00
11:00-20:00
12:00
12:00-12:00
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
18:00
19:00
20:30
SAT.03/21/2026
10:00-20:00
10:30-19:00
11:00-17:00
11:00-20:00
Millanni
11:00-20:00
11:00-20:00
12:00
12:00-12:00
12:00-12:00
HATRA
ハトラ
13:00-19:00
14:30
18:00
19:00
JFW NEXT BRAND AWARD 2026
JFW NEXT BRAND AWARD 2026
SPONSORS
OTHER AWARDS & EXHIBITIONS
SUPPORTED BY (02/12/2025)
経済産業省 / 外務省 / 知的財産戦略本部 / 独立行政法人日本貿易振興機構 / 独立行政法人中小企業基盤整備機構 / 東京都 / 一般社団法人日本経済団体連合会 / 日本商工会議所 / 東京商工会議所 / 一般財団法人 日本ファッション協会 / 一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会 / 一般財団法人 ファッション産業人材育成機構 / 一般社団法人 日本百貨店協会 / 渋谷区 / 港区 / 渋谷区商店会連合会 / 日本ジーンズ協議会